今さら人に聞けない投資用語!『長期金利』『短期金利』『イールドカーブ』ってなに?
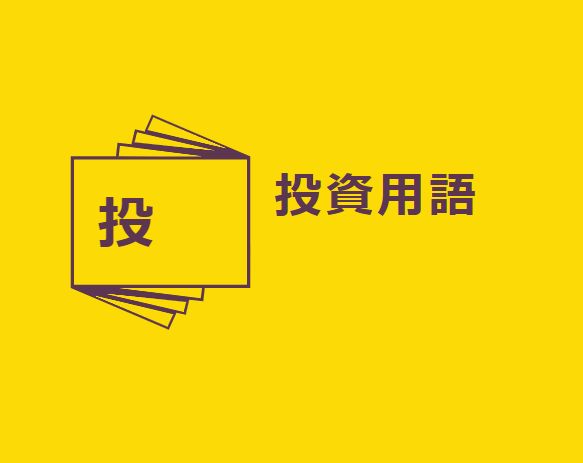
はじめに
ニュースで「長期金利が上昇」「短期金利の引き上げ」などと耳にしても、
正直、何が違うのかピンとこない人も多いと思います。
前回の記事では、中央銀行が決める政策金利について学びました。
今回は、その金利が「どんな期間を基準にしているのか」を学んでいきましょう。
実は、この「長期金利」と「短期金利」を知ると、
株価や住宅ローン、さらには為替の動きまで、経済ニュースがぐっと分かりやすくなります。
短期金利とは?──お金を“すぐ返す”世界の金利
短期金利とは、1年以内の期間でお金を貸し借りするときの金利です。
「すぐ返す約束のお金」に対する利息、と考えると分かりやすいでしょう。
たとえば、銀行同士が「今日貸して、明日返す」ような取引(=無担保コール翌日物金利)がこれにあたります。
日本では、この金利の動きをコントロールするために、日銀が政策金利を決めています。
つまり──
政策金利が上がると、短期金利も上がる。
逆に、政策金利が下がれば、短期金利も下がる。
銀行の普通預金金利や、企業の短期融資金利もこの動きに連動します。
長期金利とは?──“将来の経済”を映す金利
一方、長期金利とは、1年以上の期間でお金を貸し借りする際の金利です。
日本では代表的な指標として「10年物国債利回り」がよく使われます。
たとえば、政府が10年間お金を借りる(=国債を発行する)とき、
投資家が「10年後まで預けていいよ」と思う利回りが長期金利です。
長期金利は、将来のインフレや景気の見通しによって変動します。
つまり、“市場が未来をどう見ているか”を表す金利なんです。
たとえるなら──短期金利は天気、長期金利は気候
短期金利は、中央銀行(日銀)が決める「今日・明日の天気」。
長期金利は、市場が判断する「これからの季節(気候)」のようなものです。
たとえば、
- 日銀が金利を上げる → 短期金利がすぐに反応。
- 景気がよくなりそう → 投資家が「将来は金利が上がる」と予想して、長期金利もじわじわ上昇。
つまり
と覚えておくと、ニュースの見方がぐっと分かりやすくなります。
長期金利と短期金利の関係(イールドカーブ)
金融の世界では、さまざまな期間の金利を線でつないだものをイールドカーブ(金利曲線)と呼びます。
通常、長期のほうがリスクが高い(=期間が長いほど不確実)ため、
長期金利 > 短期金利という形が自然です。
ところが、景気が悪化する兆しがあると、
「将来は金利が下がる」と市場が予想し、短期金利のほうが高くなる“逆イールド”という現象が起きます。
これは、“不況のサイン”として注目されることもあります。
金利の違いが私たちに与える影響
- 短期金利が上がると…
→ 銀行の貸出金利やカードローンの金利が上昇。
→ 企業の資金繰りに影響が出やすい。 - 長期金利が上がると…
→ 住宅ローン(金利固定型)が上がる。
→ 国債の利回りが上がり、債券価格が下がる。
つまり、
短期金利は「企業や銀行の息づかい」に、
長期金利は「家計や投資の未来」に関わっているといえます。
長期投資家にとってのポイント
長期投資家にとって、金利は「敵」でも「味方」でもありません。
むしろ、金利の動きから経済の温度を読む“体温計”のような存在です。
- 短期金利が上がる → 景気の加熱を冷ますタイミング。
- 長期金利が上がる → 市場が「未来は明るい」と見ている可能性。
大事なのは、「上がった・下がった」ではなく、
それが、納得して投資を続けるための学びにつながります。
まとめ
- 短期金利=1年以内の金利。日銀が操作できる“政策の金利”。
- 長期金利=1年以上の金利。市場が決める“未来の金利”。
- 短期金利は天気、長期金利は気候。
- 逆イールドは景気後退のサインとされる。
- 投資家は「金利の変化」ではなく「変化の理由」に注目することが大切。



