【9月月次レポート】SBI日本高配当株式ファンドの利回りが3.46%に低下|高配当株に何が起きているのか?
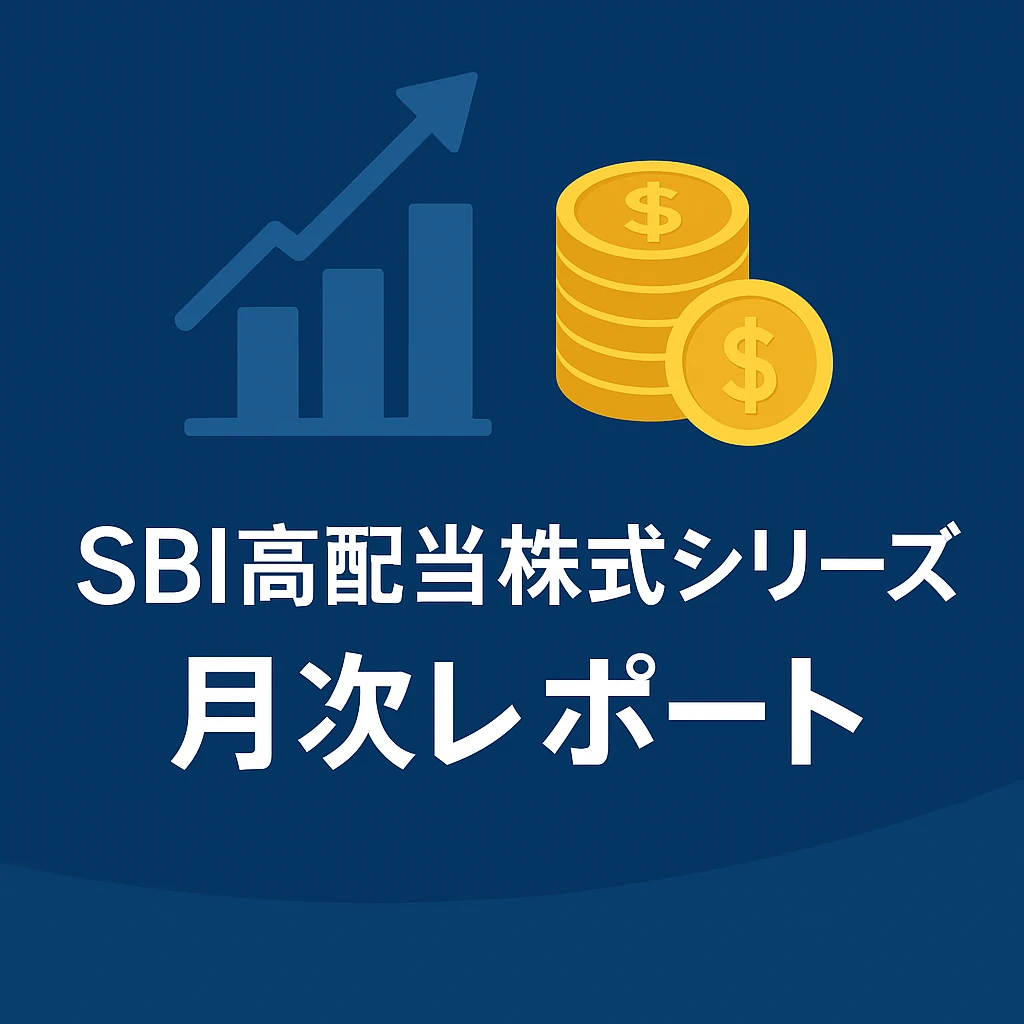
はじめに
SBIアセットマネジメントが運用する「SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)」は、
国内の高配当株を中心に安定的なインカム収益を狙う人気シリーズの一角です。
2025年9月の月次レポートでは、
基準価額が13,552円(前月比+304円)まで上昇し、純資産も1,177億円を突破しました。
一方で、注目すべきは「利回りの低下」。
ポートフォリオの配当利回りは3.46%となり、前月からやや下がりました。
これは一見ネガティブにも見えますが、背景には「株価上昇」というポジティブな要因があります。
この記事では、この利回り低下の仕組みと背景、そして今後の注目点を整理していきます。
1. 利回り低下の理由は「株価の急上昇」
まず、利回りが下がった最大の要因は分母(株価)の上昇です。
9月の日本株市場は、
- 日経平均:+5.18%
- TOPIX(配当込み):+2.98%
と、2か月連続の大幅上昇。SBI日本高配当株式ファンドの主要構成銘柄である
銀行・商社・製造業などの大型株が大きく上昇し、
その結果として配当利回りが見かけ上は低下しました。
📊 例:主力銘柄の株価上昇と利回り低下
| 銘柄 | 株価(1年前比) | 現在の利回り(目安) |
|---|---|---|
| 三菱UFJFG | 約+80% | 約3.2% |
| 三井住友FG | 約+60% | 約3.5% |
| 三菱商事 | 約+70% | 約3.1% |
| JT | 約+30% | 約4.3% |
株価が1年で30〜80%も上昇すれば、
配当金が増えても利回りは下がるのが自然な流れです。
2. 市場環境:株高+外国人投資家の買いが背景に
この株価上昇を支えたのが、外国人投資家の資金流入です。
円安基調が続く中で、
- 日本企業の輸出利益が増加
- PBR1倍割れ銘柄の改善期待
- 米国株の割高感から資金の一部が日本へ
といった要因が重なり、
金融・商社・製造業などのバリュー株が“買い戻し”の対象になりました。
特に、三菱UFJや三菱商事といった「高配当×好業績」銘柄は、
株価・配当の両面で注目を集め、ファンドの評価益に寄与しています。
3. 利回り3.46%は“悪い低下”ではない
今回の利回り低下は、
いわば“株価上昇の副作用”であり、健全な利回り低下といえます。
SBI日本高配当株式ファンドの設計は、
- 「収益性が高く」
- 「配当政策が安定」
- 「財務体質が健全」
な企業を中心に構成しており、配当を無理に増やして利回りを上げるような戦略ではありません。つまり、利回りよりも「配当の持続性」を重視しているということ。
企業の配当方針が安定していれば、
株価上昇局面で利回りが一時的に下がっても、
投資家にとっては資産全体の増加につながります。
4. 利回りが下がると“新規投資の妙味”は薄れる?
ただし、新しく買う投資家の視点では、
利回りの低下=エントリーポイントの難化を意味します。
SBI日本高配当株式ファンドのポートフォリオ利回りは3.46%ですが、
これは2024年の平均(約3.8〜4.0%)から見ると明確に低下しています。
この水準になると、
「高配当目的の新規購入」としてはやや物足りないと感じる投資家も増えるでしょう。
ただし、配当水準は維持されており、
株価が一時的に調整すれば再び利回りが戻る可能性があります。
5. 今後の注目ポイント
今後の焦点は、
配当利回りを再び押し上げる“企業側の増配”が出てくるかどうかです。
🔍 注目すべき3つの視点
- 2025年3月期決算での増配発表
- 銀行・商社・製造業は過去最高益を更新中。
- これらの企業が配当性向を引き上げれば、
ファンド全体の利回りも上向く可能性あり。
- 日銀の金融政策(利上げタイミング)
- 利上げは金融株にプラス。
- 一方で、ディフェンシブ株(通信・食品)にはマイナス要因。
- ファンドのバランス維持が試される展開。
- ファンドの組入変更
- 9月は建設セクターで「西松建設」→「インフロニアHD」に変更。
- こうした再構成で、利回りの維持+成長余地確保を図っている。
6. 投資家がとるべきスタンス
長期保有中の人へ
今の利回り低下は「資産が育っている」サインでもあります。
焦って乗り換える必要はなく、増配期待を持ちながら継続保有でOKです。
新規投資を考える人へ
短期的には割高感があります。私はこのタイミングで、大きく買うことはありません。
投資タイミングを見極められないという人は、ドルコスト平均法を活用するのも一つの手です。

おわりに
SBI日本高配当株式ファンドの利回りは3.46%と、
一時期に比べてやや低下しました。
しかしそれは、株価上昇=ファンドの信頼が高まった結果でもあります。
特に金融・商社・製造業といった高収益セクターが上昇した今、
この利回り低下はむしろ“成長と安定の両立”を示すものといえるでしょう。
長期投資家にとっては、
「一時の利回り変動よりも、配当を継続できる企業を持ち続ける」ことが大切です。
次回の10月決算での分配方針、
そして2025年春にかけての増配発表ラッシュが、
利回りの底を再び押し上げる可能性を秘めています。



