今さら人に聞けない投資用語!『騰落率』ってなに?
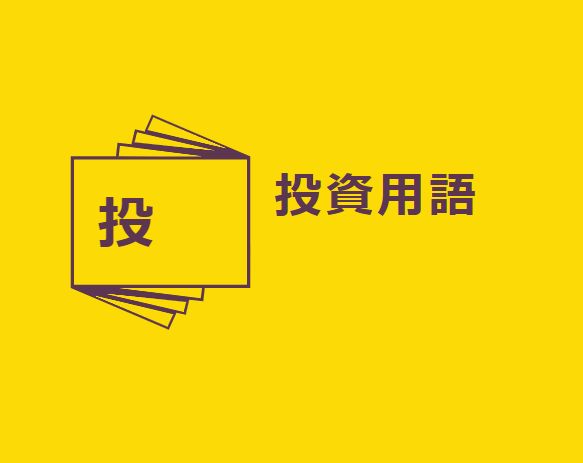
はじめに
投資に関するニュースを読んでいると、「騰落率(とうらくりつ)」という言葉がよく登場します。証券会社のレポートや新聞の株式欄、あるいはテレビの経済番組などで「今週の日経平均株価の騰落率はプラス3%」といった形で耳にすることがあるでしょう。
ただ、初心者の方からすると「株価が上がったり下がったりしたことを示すんだろうけど、具体的にどういう意味なのか」「どんな場面で役立つのか」が分かりにくい言葉でもあります。
そこで今回は、この「騰落率」について、基本的な意味から活用方法、注意点までを、分かりやすい例を交えて解説していきます。これを読めば、ニュースやレポートで出てくる騰落率を理解できるだけでなく、実際の投資判断にも活かせるようになるはずです。
騰落率とは?
騰落率とは、株価や株価指数が基準とした時点と比べて、どのくらい上昇(騰)あるいは下落(落)したのかをパーセントで示したものです。
たとえば、1か月前に1,000円だった株が現在1,100円になっていたとします。この場合は「騰落率はプラス10%」となります。逆に株価が900円に下がっていれば「マイナス10%」ということです。
つまり、騰落率を見ることで、「株価がどれくらい変化したか」を直感的に把握できるわけです。
身近な例で考える
株価の話だとイメージがつかみにくいかもしれません。そこで、日常生活の例で考えてみましょう。
あなたがスーパーでよく買う卵が、1パック200円だったとします。ある日、同じ卵が220円に値上がりしていました。このとき、値上がりした幅は20円。これを元の200円に対してパーセントで表すと「10%」の値上がりです。
株価の騰落率も同じ考え方で、基準となる価格からどのくらい変化したのかを割合で示しているにすぎません。
このように考えると、騰落率はとてもシンプルな指標だと分かりますね。
騰落率と騰落レシオの違い
ここで混同しやすいのが「騰落レシオ」です。名前が似ていますが、内容はまったく別物です。
- 騰落率 … 個別銘柄や株価指数の値動きをパーセントで表したもの
- 騰落レシオ … 市場全体で値上がりした銘柄数と値下がりした銘柄数の比率を表したもの
つまり、騰落率は「一つの株や指数がどれくらい動いたか」を見る指標で、騰落レシオは「市場全体が強いのか弱いのか」を測る指標です。
ニュースで「騰落率」と「騰落レシオ」が同じ記事に出てきても、それぞれ意味が違うことを理解しておくと混乱しません。
騰落率の活用方法
では、投資家は騰落率をどんな場面で利用するのでしょうか。具体的に見ていきましょう。
1. 銘柄の比較に使う
ある期間で複数の銘柄のパフォーマンスを比較したいとき、騰落率はとても便利です。
例えば、同じ1年間で、A社の株価は1,000円から1,100円に上昇、B社の株価は2,000円から2,100円に上昇したとします。金額だけを見ればA社は100円の上昇、B社は100円の上昇でまったく同じ。ところが、騰落率で比較すると、A社はプラス20%、B社はプラス5%となり、A社の方がパフォーマンスが良かったと判断できます。
このように金額の差ではなく割合で比較できるので、公平にパフォーマンスを評価できるのです。
2. 市場全体の動きを知る
日経平均株価やTOPIXなどの主要指数についても、騰落率がよく使われます。たとえばニュースで「今週の日経平均株価は前週末比プラス3%」と報じられれば、全体として市場が上昇傾向にあることが分かります。逆に「マイナス5%」なら、市場全体に逆風が吹いていると判断できるでしょう。
3. 投資判断の材料にする
騰落率は投資判断にも活用されます。短期間で大きく上昇している銘柄は人気を集めている証拠ですが、一方で過熱感があるサインかもしれません。逆に大きく下落している銘柄は、一時的に売られすぎて割安な可能性もあります。
もちろん騰落率だけで投資を決めるのは危険ですが、他の指標やニュースと組み合わせることで、売買のタイミングを考える参考になるのです。
注意点
騰落率は便利な指標ですが、いくつか注意すべきポイントがあります。
期間によって印象が変わる
同じ銘柄でも、どの期間を基準にするかによって騰落率は大きく変わります。たとえば「直近1週間でプラス5%」といっても、「過去1年間で見ればマイナス15%」ということもあり得ます。ニュースやレポートで騰落率を目にしたときは、必ず「どの期間を基準にしているか」を確認しましょう。
一時的な値動きにすぎない場合もある
短期的な騰落率は、市場の一時的な動きに大きく左右されます。例えば決算発表や為替変動など、特定のイベントが原因で株価が急騰・急落することも珍しくありません。そのため、短期の騰落率だけに注目して投資判断すると、思わぬ損失につながることもあります。
騰落率が高い=必ず良い銘柄ではない
プラスの騰落率が大きい銘柄は「好調」と受け取られがちですが、それが一時的なブームや材料による急騰であれば、長期的に安定して成長する保証はありません。逆にマイナスが大きくても、業績が堅実な企業なら一時的な調整にすぎないこともあります。
実際の事例で考える
ここで実際の相場の事例を挙げてみましょう。
たとえば、2020年のコロナショックの際、多くの株価指数は短期間で大幅に下落しました。日経平均株価も数週間で20%以上のマイナスとなり、大きな騰落率の下落を記録しました。ところが、その後の景気刺激策やワクチン普及などにより急速に回復し、年末にはむしろプラスの騰落率となりました。
この事例から分かるのは、「短期的な騰落率に一喜一憂せず、長期のトレンドも見ることが大切」という点です。
まとめ
騰落率とは、株価や指数が基準からどれだけ上昇・下落したかをパーセントで示すシンプルな指標です。
- 一つの銘柄や指数の値動きを分かりやすく示す
- 複数銘柄の比較や市場全体の動向把握に役立つ
- 投資判断の材料にもなるが、期間や背景を考慮することが重要
投資の世界ではさまざまな指標が登場しますが、騰落率はその中でも特に直感的で理解しやすいものです。ニュースやレポートに出てきたときに「なるほど、この銘柄はこの期間でこれだけ動いたのか」と理解できるようになれば、情報収集の精度が一段と高まります。
ただし、騰落率だけで判断せず、業績や配当、他の市場指標と組み合わせて総合的に判断することが大切です。騰落率を正しく理解して活用すれば、投資判断における視野が広がり、より堅実な資産形成につながるでしょう。



