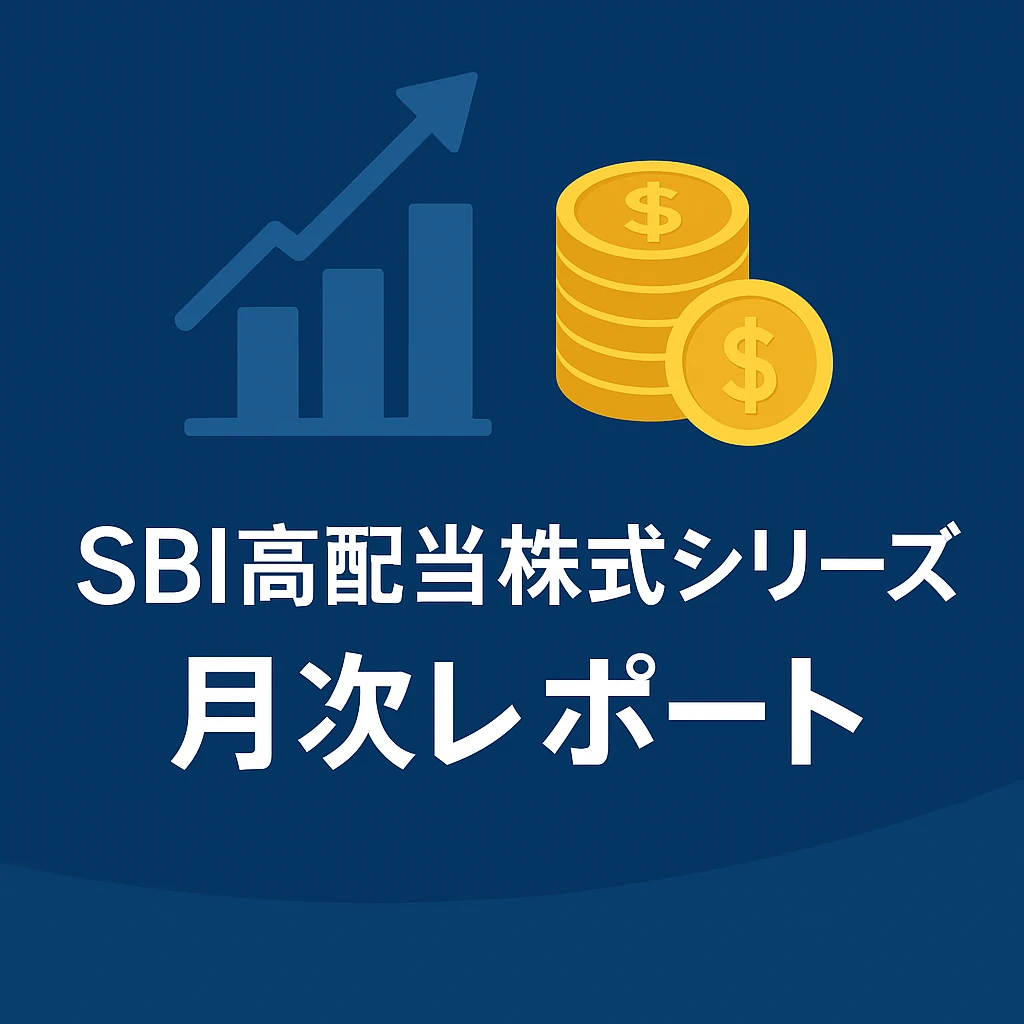楽天SCHDの信託報酬が引き下げ!SBI・SCHDと徹底比較【2025年最新版】

はじめに
2025年5月、楽天・SCHD(楽天・シュワブ・高配当株式・米国ファンド)が信託報酬の引き下げを発表し、SBI証券で取り扱うSBI・SCHDとの競争が一段と激しくなってきました。
この2つのファンドは、いずれも米国の人気ETF「SCHD」を投資対象とした高配当株ファンドですが、購入できる証券会社や分配月、コスト構造などに違いがあります。
本記事では、両ファンドの主な違いを整理し、どちらを選ぶべきかを投資家目線で解説します。
そもそもSCHDとは?
「SCHD」とは、米国の大手証券会社チャールズ・シュワブ社が提供するETF「Schwab U.S. Dividend Equity ETF」のティッカーシンボルです。
正式名称は「シュワブ米国配当株式ETF」で、安定した配当実績を持つ米国の優良企業に投資する高配当ETFとして、近年大きな注目を集めています。
構成銘柄はコカ・コーラやホームデポ、ブロードコムなど、米国を代表する企業が多く、過去10年で分配金も増配傾向。
さらに、信託報酬がわずか0.06%台と低コストである点も、長期投資家にとって魅力です。
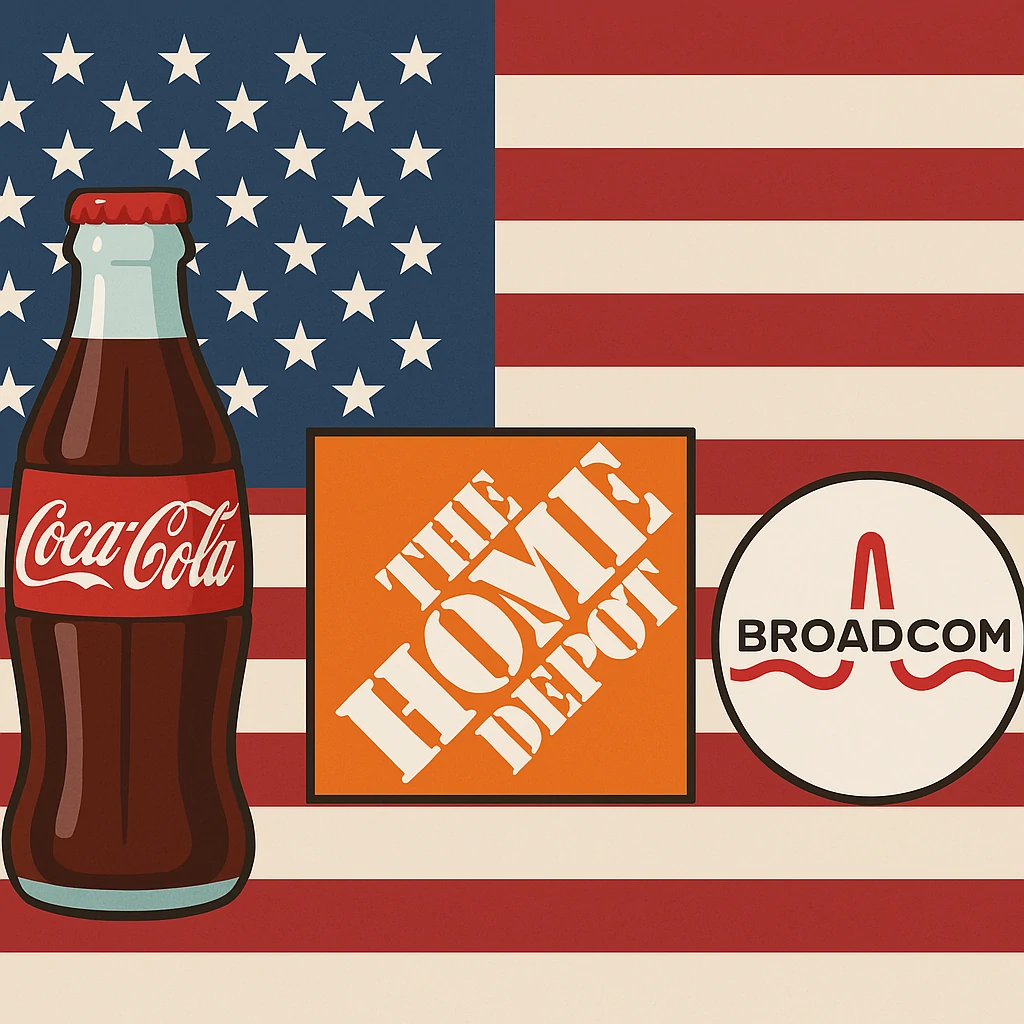
ETFそのものではなく“投資信託版SCHD”が人気の理由
「じゃあ本家のSCHD(ETF)を買えばいいのでは?」と思われるかもしれませんが、実際には以下の理由で日本国内の投資信託版SCHD(楽天・SCHDやSBI・SCHD)が人気を集めています。
① 円建てで購入できる
ETFは米ドルでの取引が基本ですが、投資信託版なら円で購入・運用が可能。為替の両替手数料を気にせず、積立設定もしやすい点が魅力です。
② NISA成長投資枠で利用可能
ETFは一部の制度と相性が悪いですが、投資信託は新NISAの対象商品として取り扱われており、成長投資枠での積立が可能です。
③ 分配金も円建てで支払われる
ETFではドル建てで分配金が支払われますが、投資信託版では円建てで分配金が支払われます。ここでも為替の両替手数料が必要ありません。
このような背景から、日本の証券会社が「SCHDを投資対象にする投資信託」を設定し、投資家のニーズに応える形で広まりました。
楽天SCHDとSBI・SCHDの違いとは?
現在、代表的なSCHD連動ファンドには「楽天・SCHD」と「SBI・SCHD」の2本があります。
2025年5月に楽天・SCHDの信託報酬が引き下げられることで、両者のコストはほぼ横並びとなりました。以下で詳しく比較してみましょう。
| 比較項目 | 楽天・SCHD | SBI・SCHD |
|---|---|---|
| 投資対象 | SCHD(ETF) | SCHD(ETF) |
| 購入できる証券会社 | 楽天証券 | SBI証券 |
| 信託報酬(税込) | 0.1238%(2025/5/23~) | 実質0.1238%程度(信託報酬0.0638%+ETF経費) |
| 分配月 | 2・5・8・11月 | 3・6・9・12月 |
| 為替ヘッジ | なし | なし |
| 最低投資額 | 100円~ | 100円~ |
ポイント① 信託報酬は実質ほぼ同じに
これまで楽天・SCHDは0.192%の信託報酬で、SBI・SCHDに比べてやや高コストでしたが、今回の信託報酬引き下げ(0.1238%)により、SBI・SCHDの実質的なコストと並ぶ形になりました。
SBI・SCHDは投資信託本体の信託報酬が0.0638%と非常に低く、加えてSCHD自体の運用経費が含まれ、実質0.1238%程度とされています。楽天側もこの水準に合わせることで、より多くの投資家の支持を狙っています。
ポイント② 分配月が異なることで分散が可能に
楽天・SCHDは2・5・8・11月に分配金が支払われ、SBI・SCHDは3・6・9・12月に分配されます。
つまり、両方を保有すれば、分配金の受け取り時期を分散させることが可能です。
これは、生活資金を分配金で補いたい投資家にとって魅力的な戦略の一つでしょう。
ポイント③ 取扱証券会社の違いに注意
- 楽天・SCHDは楽天証券専用
- SBI・SCHDはSBI証券専用
現時点では、それぞれのファンドを他の証券会社で購入することはできません。
そのため、どちらを選ぶかは「どこの証券口座を持っているか」が現実的な選択軸となります。
おわりに:どちらを選ぶべきか?
投資対象やコスト、分配頻度に大きな差がなくなった今、最終的には以下のように選ぶのが良いでしょう。
- 楽天証券ユーザー → 楽天・SCHD
- SBI証券ユーザー → SBI・SCHD
- 分配金を分散させて受け取りたい人 → 両方を組み合わせる
どちらも、「本家SCHDを円建てで手軽に投資できる」という魅力を持っています。
分配金戦略や口座事情に応じて、あなたにとって最適な選択をしてみてください。