今さら人に聞けない投資用語!『優待利回り』ってなに?
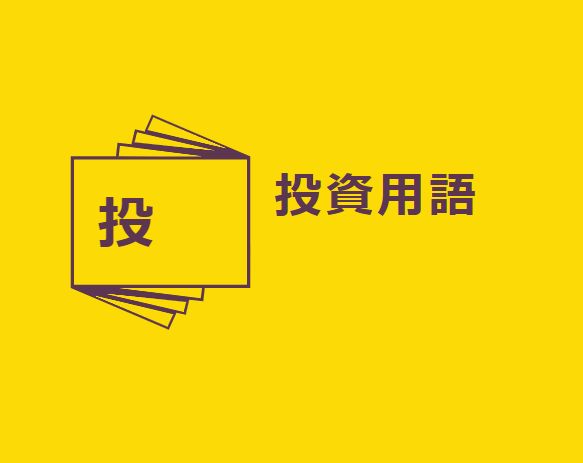
はじめに
株式投資を始めるとよく聞く言葉のひとつが「株主優待」。
「お米券が届いた!」「カタログギフトがもらえた!」という話をSNSで見たことがある人も多いのではないでしょうか?
そんな株主優待の“お得度”を数字で表したものが優待利回りです。
この記事では、優待利回りの意味と計算方法、配当利回りとの違い、注意すべきポイント
を、具体例を交えてやさしく解説します。
優待利回りとは?
優待利回りとは、株主優待でもらえるモノやサービスの価値を、株価に対する割合で表したものです。
つまり、「投資金額に対して、どのくらいの“優待の価値”が戻ってくるか」を数値化した指標です。
優待利回り(%)=優待の金額換算価値÷株価×100
たとえば、ある企業の株価が1,000円で、
100株(=10万円)を持っていると3,000円分の優待がもらえる場合―
3,000÷100,000×100=3%
このときの優待利回りは3%となります。
配当利回りとの違い
配当利回りは「現金でもらえるリターン」、
優待利回りは「モノやサービスでもらえるリターン」です。
| 項目 | 配当利回り | 優待利回り |
|---|---|---|
| もらえるもの | お金(現金) | モノ・サービス・割引券など |
| 受け取り時期 | 年1~2回が多い | 年1~2回(企業による) |
| 課税の扱い | 所得税・住民税の対象 | 基本的に非課税(現物) |
| 使い道 | 自由に使える | 商品や店舗で使う形が多い |
両方を合わせた「総合利回り(配当+優待)」で考える投資家も多く、
たとえば「配当3%+優待2%=総合5%」というように評価します。
優待の種類いろいろ
企業によって、株主優待の内容はさまざまです。
代表的なタイプを3つ紹介します。
- 自社製品タイプ
→ 食品会社・化粧品会社など。例:カゴメ、キユーピー、花王。 - 金券・クオカードタイプ
→ どこでも使えるため人気。例:KDDI、オリックス(旧優待)。 - カタログギフトタイプ
→ 自分で好きな商品を選べる。例:オリックス、ANA、JAL。
最近は、株主優待を電子クーポン化する企業も増えており、
スマホアプリで使える形に変わりつつあります。
優待利回りの目安
優待利回りは、一般的に1〜3%程度が多く、
配当と合わせて「総合4〜6%」になれば魅力的とされています。
| 優待利回り | 評価の目安 |
|---|---|
| 1%未満 | 控えめ(記念品など) |
| 1〜2% | 平均的(人気企業が多い) |
| 3〜5% | 高水準(長期優待や人気ギフト) |
| 5%以上 | 要注意(内容変更・改悪のリスク) |
優待利回りを計算するときの注意点
- 優待の“実際の価値”は人によって違う
→ 3,000円分の食事券でも、使わない人にとっては価値ゼロです。
→ 利回り計算は「自分が使う前提」で考えるのが現実的。 - 長期保有が条件の企業も多い
→ 「3年以上保有で優待額アップ」などの制度あり。
→ 一時的に買ってももらえないケースがある。 - 突然の“優待廃止”もある
→ 近年はコスト削減で優待制度をやめる企業も増加。
→ 配当中心へシフトしている傾向あり。
優待利回りの計算例(実際のイメージ)
たとえば、ある飲食チェーンの株価が2,000円で、
100株(20万円)を保有すると年間4,000円分の食事券がもらえる場合:
4,000÷200,000×100=2%
さらに年間5,000円の配当があれば――
配当利回り2.5%+優待利回り2%=総合利回り4.5%!
こうして「配当+優待」でリターンを考えると、投資判断がより具体的になります。
優待利回りを重視するなら「生活との相性」が大切
優待は“お得さ”だけでなく、自分の生活に合っているかが大事です。
- よく行くお店(外食・ドラッグストア・スーパー)
- よく使うサービス(通信・交通・旅行)
- 家族で使えるもの(食品・日用品)
たとえば、外食が多い人は「すかいらーく」や「吉野家HD」、
旅行好きなら「ANA」「JAL」などが候補になります。
自分の生活に“ちょっとしたプラス”を与えるのが株主優待の魅力です。
まとめ
- 優待利回りは、株価に対する優待の価値を数値で表したもの。
- 計算式:優待の金額換算 ÷ 株価 × 100。
- 配当利回りと組み合わせた「総合利回り」で判断するとわかりやすい。
- ただし、優待の価値は人によって異なり、“使えるかどうか”が本当の利回り。
- 長期保有条件や優待廃止にも注意が必要。


