ゴリラ先生のやさしい投資教室│第28回 なぜ日本では終身保険や定期預金が信仰されてきたのか?時代別に読み解く
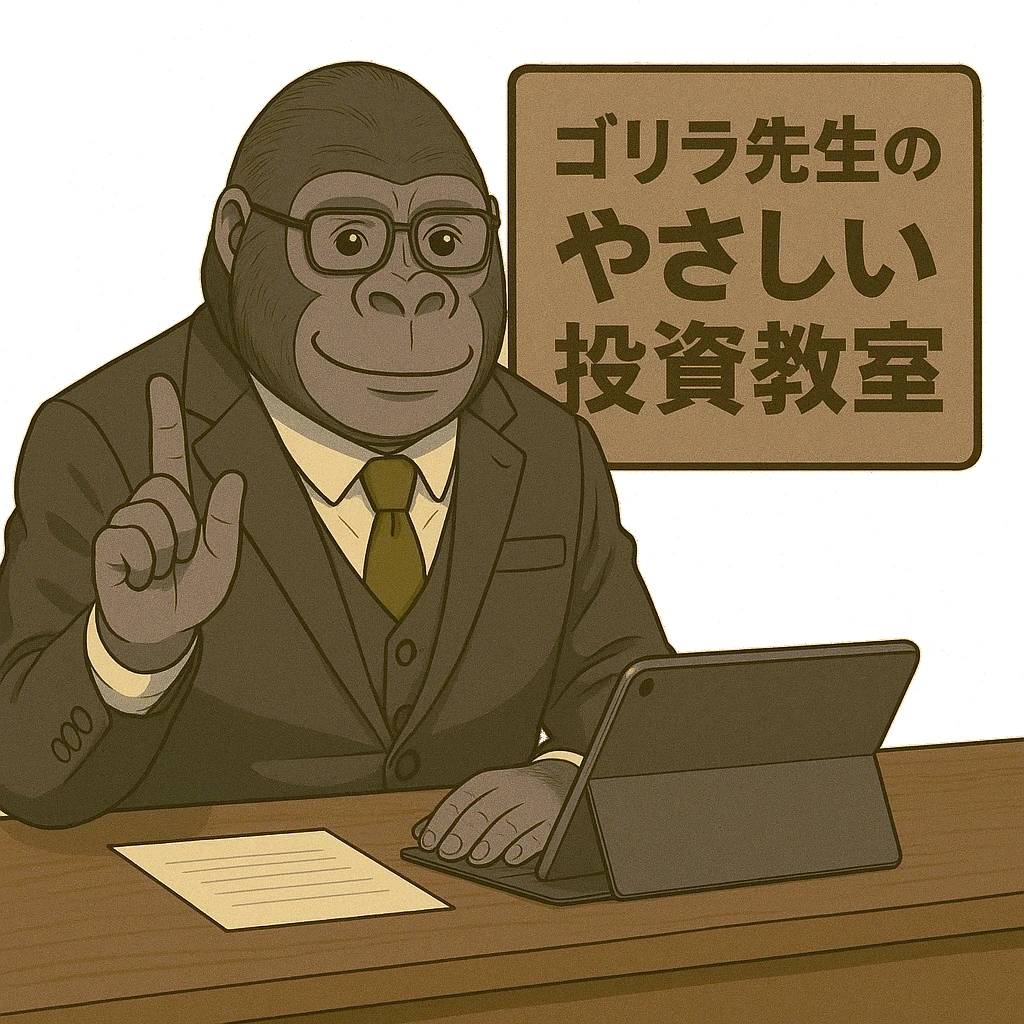
スーツとメガネがトレードマークの、頼れるお金のナビゲーター。
知識は豊富だけど説明はやさしく、質問には真剣に向き合ってくれる。
今日もハルトとミナミの“なぜ?”に、穏やかに答えてくれる先生。

YouTubeで見たFIRE動画に憧れて、投資に興味を持った13歳。
テンバガーや仮想通貨にすぐ飛びつく、元気でちょっとビビりなタイプ。
まだ投資は未経験で、ミナミやゴリラ先生に教わりながら勉強中。
SNSで投資を知り、「お金の勉強って大事かも」と思い始めた13歳。
慎重派で、定期預金や貯蓄型保険に安心感を覚えるタイプ。
ハルトの勢いに振り回されつつも、一緒に少しずつ学んでいる。
はじめに
ねえミナミ、うちのおばあちゃんに投資の話したんだけどさ、“定期預金が一番安全!”って言うんだよ。なんでお年寄りって定期預金や保険が好きなんだろう?
たしかに、おじいちゃんやおばあちゃんの世代は“預金と保険こそ正義”って価値観が強い気がするよね。先生、どうしてなんでしょうか?

とても良いご質問です。時代ごとの経済環境が、その時代の“合理的な選択”を形づくってきたのです。今日は年代ごとに、歴史と家計のリアルをたどってみましょう。
戦後~高度経済成長期:「預けて増える」が常識だった時代

戦後の復興から高度経済成長期にかけては、賃金が上がり、物価も伸び、経済全体が右肩上がりでした。銀行預金にはそれなりの金利がつき、郵便貯金も“とにかく貯めれば増える”のが体感できた時代です。
ボクたちのおじいちゃんやおばあちゃんが若いころの時代だね。

そうですね。加えて、終身保険や養老保険は“家族を守る安心”の象徴でした。社会保障が十分に整っていなかったため、民間保険は“もしものときのセーフティネット”。さらに企業や地域社会も『貯蓄・保険は善』という空気を後押ししていました。
当時の人にとっては預金=効率的、保険=必要。合理的だったんですね。

おっしゃるとおりです。『銀行に預ける』『保険に入る』は、当時の最適解だったのです。
~80年代:安定成長と“学資・養老”の文化

成長が少し落ち着いた70~80年代でも、ボーナス文化や学資保険が家計の柱でした。親は“子の学費は保険で積み立てる”、住宅は長期ローン+ボーナス払い、余剰資金は定期預金へ。『計画的に積み上げる』発想が強かった時代です。
積み上げるって言うけどさ。ボクたちみたいに積立投資はしてなかったの?
それ私も気になってた。先生、当時は投資ってあまり一般的ではなかったのでしょうか

当時の株式投資は機関投資家中心で、個人の投資インフラ(ネット証券、積立投資の普及、低コスト投信など)は整っていませんでした。だから“貯める・守る”に家計が向かいやすかったのでしょうね。
1990年代~2000年代初頭:バブル崩壊、ゼロ金利、そして“価値観の慣性”

ところが1990年のバブル崩壊で状況は一変します。地価・株価が長く低迷し、預金金利は超低金利へ。家計は“安全第一”の意識をさらに強め、結果として預金・保険の信仰はむしろ固まりました。
え?金利がほぼゼロでも、やっぱ預金最強って思ってたの?

長年の成功体験は強力です。“預ければ増えた”記憶は簡単には書き換わりません。さらに当時は保険の販売力も強く、貯蓄保険が『確実に積み立てられる安心』として選ばれやすかった。結果、“安全神話の慣性”が働いたのです。
理屈では“増えない”と分かっても、心理的安全を買っていた面もあるんですね。

ええ。経済が停滞し不確実性が高いと、人は“分かりやすい安心”に向かいます。
2000年代半ば~リーマン前:『貯蓄から投資へ』の号砲と現実のギャップ

2000年代に入ると国は“貯蓄から投資へ”を掲げ、投資教育や制度整備が始まります。とはいえ、コストの高い金融商品や、“難しそう”という心理的ハードルが壁に。投資は少しずつ広がったものの、家計の主役は依然として預金と保険でした。
スマホで調べたりできないの?

当時の携帯電話は簡易的なインターネット機能しか備えておらず、いまのように低コストのインデックス投信やネットでの比較・情報が潤沢ではありませんでした。『やってみよう』と一歩踏み出すには、材料が少なかったのです。ただ、この時期からインデックス投資信託に投資していた人は、既にFIREを達成したという話は耳にしますね。
地道に積み重ねた結果が花開いたんですね!
2008年リーマンショック~アベノミクス初期:恐怖と再起のはざまで

話を戻しましょう。2008年のリーマンショックは市場への恐怖を社会に刻みました。“投資=怖い”の印象が再び強化され、家計の資金は守りへ。いっぽう政策は金融緩和へ進み、株価や為替は次第に改善。ここからインデックス投資や積立の優位が少しずつ認知されていきます。
恐怖体験のあとに投資続けるの、メンタル要るよなぁ。
だからこそ、“長期・分散・積立”という手法が意味を持つんですね。

そのとおり。時間を味方につけ、上下動そのものを受け止める設計が、投資を“続けられる”力になります。
2010年代後半~現在:低コスト投信、NISA/iDeCo、そして“投資はインフラ”へ

さらに時代は進むと、低コストのインデックスファンドが一般化し、NISA・iDeCoといった制度も整って、投資は一気に身近になりました。SNSや動画で学べる環境が整い、若年層の積立デビューが常識に。みなさんのS&P500やオルカンの積立も、この流れの中にあります。
ボクたちは時代の最先端ってワケだな!
先生、いまでも“終身保険や定期預金が一番”という家庭は多いですが、どう受け止めれば良いでしょうか。

否定ではなく整理が大切です。保険は保障としての役割、定期預金は流動性と安全の役割。そこに“増やす”役割として長期・分散・積立の投資を置く。役割分担で考えるのです。
小さな実例でイメージを固めよう(会話で板書)

たとえば、家計を“3つの箱”でたとえてみましょう。
- 生活防衛の箱:当座資金・定期預金。数か月分の生活費を確保し、急な出費に対応。
- 保障の箱:掛け捨て中心の生命保険・医療保険で大きなリスクに備える(必要額は家族構成で設計)。
- 成長の箱:NISAやiDeCoで低コストのインデックスを長期・分散・積立。
“役割が違う箱”。これならボクでも混乱しない。お菓子の箱は別枠で。
それは“浪費の箱”だね…。でも、祖父母世代にも説明しやすいです。“全部を投資に”ではなく、“必要な安心は残して、増やす部分は時代に合わせて”と。
終身保険・定期預金が“信仰”になった心理

最後に、なぜ“信仰”になるのかを心理面から整理します。
- 成功体験の固定化:かつての“預けて増える”が強い記憶として残る。
- 不確実性への防衛:未知のもの(投資)より、既知の安心(預金・保険)へ。
- 社会的規範:職場・親族・地域で“良い家計は貯蓄と保険”という規範が共有されやすい。
- 販売接点の強さ:身近な人から勧められる保険は心理的ハードルが低い。
背景がわかると、対立せずに対話できますね。
うちのお爺ちゃんが“投資なんて危なくないか”って心配してた理由が、なんとなくわかってスッキリした!

少額投資や長期投資の安全性も併せて伝えると、安心してもらえるかもしれませんね。
これからの指針:否定ではなく“更新”を

結論はシンプルです。昔の常識は、当時は合理的だった。ただ、環境は変わった。だから私たちは“否定”ではなく“更新”を選びましょう。
- 守る(預金・保険)は残す。
- 増やす(長期・分散・積立の投資)を加える。
- 仕組み化(自動積立・リバランス)で“続けられる”を優先。
よし、ボクは“お菓子積立”を“投資積立”に更新だ!
それ、口座からお菓子に流出してるだけだよね?まずは“浪費の箱”の上限を決めたほうがいいんじゃない?

お二人とも素晴らしいですね。家計は設計、投資は習慣。この二つが揃えば、時代が変わっても揺らぎません
まとめ
- 終身保険や定期預金が信仰されたのは、当時の環境では合理的だったから。
- バブル崩壊・超低金利を経ても、成功体験の慣性と安心を求める心理で価値観は残った。
- 現在は低コスト投信・NISA/iDeCoが整い、“守る”と“増やす”の役割分担で家計を設計できる。
- 祖父母や親世代とは対立でなく対話を。“全部を替える”ではなく、必要な安心を残しつつ、増やす部分を時代に合わせて更新する。
オッケー、今日のまとめ:“昔の正解を尊重しつつ、いまの正解にアップデート”。これでいこう!
はい。まずは生活防衛資金と保障を確認して、積立は“淡々と”。ありがとうございました、先生。

こちらこそ。お二人の前向きさが、何よりの“長期の味方”です。


