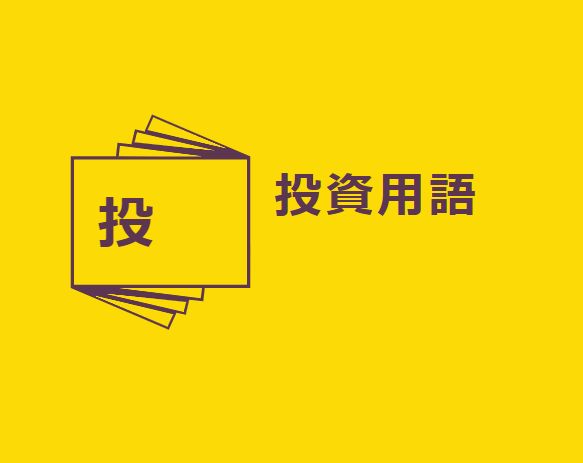金融庁「令和8年度 税制改正要望」資産運用に関わる注目ポイントを解説

はじめに
金融庁は2025年8月末、「令和8年度(2026年度)税制改正要望」を発表しました。
大きな話題となったのは「NISAつみたて投資枠を18歳未満に開放する方向で検討」という項目ですが、それ以外にも資産運用に大きな影響を与える要望が盛り込まれています。
今回はその中から、特に個人投資家が注目すべき3つのテーマを取り上げます。
- 金融所得課税の一体化(損益通算範囲の拡大)
- 暗号資産の課税方式の見直しとETF導入の検討
- NISA制度の利便性向上(手続き簡素化と対象商品の安定性)
いずれも、資産運用の実務や投資家の行動に直接関わってくる重要なトピックです。
1. 金融所得課税の一体化 ― 損益通算の範囲拡大へ
まず注目すべきは「金融所得課税の一体化」です。
現在、株式や投資信託などの売却益や配当は20.315%の申告分離課税で、損失が出た場合は同じ区分内(株・投信・ETFなど)で損益通算が可能です。しかし、預貯金の利子や一部のデリバティブ取引は損益通算の対象外となっています。
これがもし改正されれば、株式や投資信託の損失を預金利子やデリバティブ益と相殺できるようになります。
投資家への影響
- 節税効果が高まる
株式などで損失が出た場合、これまで「利子や他の金融商品で得た利益には課税されるだけ」でした。今後はそれを相殺できるため、トータルの税負担を軽減できる可能性があります。 - 幅広い商品への投資がしやすくなる
これまでは「損益通算できないから手を出しにくい」と考えていた金融商品にも投資しやすくなります。 - 税制の公平性が高まる
同じ金融所得でも「課税体系がバラバラ」という状況が是正されることで、投資家にとって分かりやすい制度になるでしょう。
これは投資家にとって非常にポジティブな改正であり、資産運用を複数商品で行う人にとってメリットが大きいと考えられます。
2. 暗号資産の課税方式見直しとETF導入
次に注目なのが、暗号資産(仮想通貨)関連です。
現在、暗号資産の利益は雑所得として総合課税の対象になっています。給与所得などと合算され、最高で55%もの税率が課されるため、暗号資産投資を敬遠する個人投資家も少なくありません。
これに対し金融庁は、株式やFXと同様の20%分離課税にする方向で検討しています。
投資家への影響
- 暗号資産投資が一気に身近になる
高税率が障壁だった暗号資産市場に、個人投資家が参入しやすくなります。 - 資産形成の選択肢が拡大
株式・投信に加えて、暗号資産を「長期保有の一部」として組み込む投資家が増えるかもしれません。
さらに、要望の中には 「暗号資産ETF(上場投資信託)の導入」 も視野に入っていることが明記されています。
海外ではすでにビットコインETFやイーサリアムETFが上場しており、個人投資家が証券口座から手軽に暗号資産に投資できる環境が整いつつあります。日本でも同様のETFが導入されれば、
- 直接ウォレットを管理する必要がない
- 取引所リスクを避けつつ投資できる
- 税制上も透明性が高まる
といったメリットが期待されます。
暗号資産は値動きの激しいリスク資産であることに変わりはありませんが、課税方式の見直しとETFの導入は「安心して投資できる仕組み」を整える第一歩になるでしょう。
3. NISA制度の利便性向上
3つ目はNISA制度の使いやすさに関する要望です。
所在地確認手続きの簡素化
現行制度では、NISA口座を開設してから10年ごとに「住所確認」などの手続きが必要ですが、これを簡素化する方向です。
長期投資を前提とするNISAで、手続きが煩雑だと途中で離脱する投資家も出かねません。制度がシンプルになることは、利用者にとって安心材料となります。
NISA対象商品の安定性
また、NISAの対象商品についても「利用者に長期的に安心して投資してもらえるようにする」ことが強調されています。
実際、これまでに成長投資枠の商品が早期償還した例もあり、投資家に不安を与えました。金融庁がこの点を意識して要望に盛り込んだのは、長期投資を促す制度設計として重要な意味を持ちます。
今回の要望から見える方向性
今回の金融庁の要望を総合すると、日本の資産運用制度は以下の方向に進もうとしているといえます。
- 長期投資をより安心して続けられる環境づくり(NISAの改善)
- 課税制度のわかりやすさ・公平性の向上(金融所得課税の一体化)
- 新しい資産クラスへのアクセス拡大(暗号資産の分離課税・ETF導入)
いずれも「貯蓄から投資へ」を一段と加速させる狙いがあることは明らかです。
まとめ
金融庁の令和8年度税制改正要望では、未成年へのNISA拡大が注目を集めましたが、それ以外にも資産運用に直結する重要な改革案が含まれています。
- 金融所得課税の一体化による損益通算拡大
- 暗号資産の分離課税化とETF導入検討
- NISA制度の手続き簡素化と対象商品の安定性確保
これらはいずれも、投資家にとって使いやすく、公平で、安心できる資産形成環境を整えるものです。
資産形成を続けていくうえで、これらの制度変更が実現すれば、大きな追い風となるでしょう。投資家は今後の議論の行方に注目しながら、自らの資産運用にどう影響してくるのかを意識しておくことが大切です。