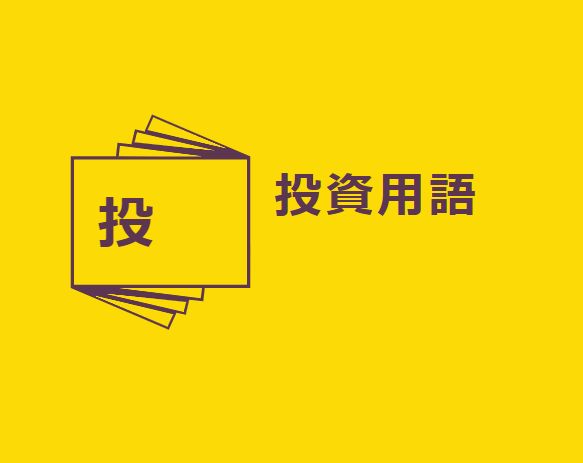『インデックスファンドを買っておけばOK』の落とし穴!非分散型インデックスファンドの解説と注意点

はじめに
投資初心者の間でよく耳にするアドバイスのひとつが、
「とりあえずインデックスファンドを買っておけば間違いない」という言葉です。
確かにこれは投資の基本ともいえる考え方ですが、その「インデックスファンド」がどんな指数に連動しているかによって、その中身は大きく異なります。
実は、「インデックスファンド=分散されていて安全」という思い込みには落とし穴があります。
この記事では、インデックスファンドの基本から、「非分散型インデックスファンド」の代表例と注意点、そして長期投資に適したインデックスファンドの選び方までを丁寧に解説します。
インデックスファンドとは?
インデックスファンドとは、ある特定の指数(=インデックス)に連動するように運用される投資信託のことです。
- たとえば「日経平均株価」や「S&P500」など、市場全体の動きを示す指数に連動します。
- 基本的に人の判断で銘柄を選ばず、指数に合わせて機械的に銘柄を保有します。
これにより、運用コストが低く、投資初心者にも取り組みやすい商品として広く普及しています。
投資の世界で“暗黙の前提”となっているインデックスファンドとは?
投資の世界で「インデックスファンドを買う」と言われたとき、
通常は「時価総額加重平均型の、広範囲に分散されたインデックスファンド」を意味します。
具体的には:
- S&P500連動型インデックスファンド(米国の主要500社に分散投資)
- 全世界株式(オルカン)連動型ファンド(世界中の株式に分散)
これらは、国・地域・業種・企業規模のすべてに分散されたバランス型のインデックスファンドです。
投資家の多くが「インデックス=安全・分散型」と考える背景には、これらのファンドの存在があります。
でも、インデックスファンド=分散投資とは限らない
ここで大切なのは、すべてのインデックスファンドが広く分散されているわけではないという事実です。
指数(インデックス)の種類によっては、一部の業種や銘柄に極端に偏ったインデックスファンドも存在します。
つまり、インデックスファンドには大きく分けて2種類があるのです。
| 種類 | 特徴 |
|---|---|
| 分散型インデックスファンド | 全体市場の時価総額に基づいて広く分散(例:S&P500、オルカン) |
| 集中型インデックスファンド | 一部の企業・セクターに偏った指数を対象とする(例:FANG+) |
代表例:集中投資型インデックス「NYSE FANG+」
たとえば、「FANG+(ファングプラス)指数」に連動するインデックスファンドをご存じでしょうか?
この指数は、以下の10社のみで構成されています:
- Meta(旧Facebook)
- Amazon
- Apple
- Netflix
- Alphabet(Google)
- Microsoft
- NVIDIA
- Tesla
- Snowflake
- AMD
いずれも世界的な有名IT・テクノロジー企業ばかりで、指数の中身は「超ハイテクグロース株」にほぼ限定されています。
確かに過去数年間で目覚ましい成長を遂げた企業群ですが、これは分散型インデックスとは言えません。
FANG+型ファンドの注意点
- ✅ テクノロジーセクターに集中投資している
- ✅ 株価の変動が激しく、ハイリスク・ハイリターン
- ✅ 特定の国・企業の業績や政策に強く左右される
- ✅ 長期低迷の可能性も排除できない(ITバブルのようなケース)
こうした指数に連動するファンドも「インデックスファンド」ではありますが、
それはあくまで「特定テーマへの集中投資を指数化したファンド」にすぎません。
長期投資の主軸にすべきは「時価総額加重型の分散インデックス」
長期投資において主軸にすべきなのは、あくまで広範囲に分散された、時価総額加重平均型のインデックスファンドです。
代表例:
- S&P500連動型ファンド(例:eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)など)
- 全世界株式(オルカン)連動型ファンド(例:eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)など)
これらは:
- 国や業種、企業規模にバランスよく分散されており、
- 長期の経済成長をまるごと取り込む設計になっている
つまり、個別テーマに左右されにくいため、安定的な成長を期待しやすいのです。
まとめ:「インデックスファンド=安心」は思い込みに注意
- インデックスファンドと一口に言っても、中身は指数次第で大きく異なる
- 分散された安全設計なのか、テーマ集中型なのか、よく確認してから買うことが大切
- 長期投資の中核は、「S&P500」や「オルカン」のような時価総額加重平均型のファンドに据えるべき
- 集中型インデックス(FANG+など)は、補助的な短期テーマ投資として捉えるのが無難